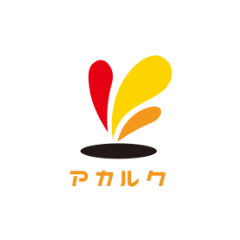1.はじめに:広がる支援と残る距離感
近年、日本におけるLGBTQ+への支援の輪は確実に広がっています。首都圏では企業の取り組みが進み、毎年東京・代々木公園で行われるTokyo Prideを始めとするプライドイベント(LGBTQ+コミュニティが自分たちの存在や権利を可視化し、社会的認知を高めるためのイベント)は年々規模を拡大し、企業の協賛や参加も増えてきています。
しかし、その一方で、人々は本当に「身近な隣人」としてLGBTQ+の存在を認識できているのでしょうか。
多くの場合、LGBTQ+に対する認識は「差別はよくない」「社会として認めるべきだ」という抽象的な賛同は高まっていても、家族や友人、職場の同僚など身近な人が当事者だった場合には、まだ抵抗感を示す人がいるのも現状のようです。最近の電通の調査では、非当事者の83.8%が「自分の子どもが当事者でも愛をもって接したい」と答えたものの、実際に当事者の子どもを持つ親では66.8%に低下しました(出典:電通「LGBTQ+調査2023」)。
、LGBTQ+に理解を示す人、好意的に包摂しようとする人は年々増加する一方で、「家族や親しい友人が当事者だったら戸惑う」と答える人はどの調査でも一定の割合で存在しています。例えば上記の電通の調査では、受け入れたいと答える人が8割を超えるにもかかわらず、実際に行動する人は2割未満にとどまることが報告されています(出典:電通「LGBTQ+調査2023」)。このギャップは、表面的な受容と、実生活における距離感の乖離を示していると言えるでしょう。
なぜこのギャップが生まれるのでしょうか。その理由の一つは、LGBTQ+が「見えにくい」属性であることです。障害や国籍など、他のダイバーシティ領域での「違い」は比較的可視化されやすいのに対し、性的指向や性自認は外見からは分かりません。結果として、隣人の問題として捉えられず、理解や共感が「概念的」なものにとどまり、具体的な行動や支援につながりにくいのではないでしょうか。
本記事では、特に地方で行われているプライドイベントに注目し、その実情や課題を通して「可視化」の意義を明らかにし、そしてそこに企業がどう関わり得るのかを探ります。
2.可視化の力とプライドイベント
プライドイベントは、このLGBTQ+の「見えにくさ」を補う一つの手段です。パレードやフェスティバルは、当事者が声を上げ、社会に存在を示す貴重な場であり、地域社会に「ここにもいるのだ」という実感をもたらします。こうしたイベントは、単なる祝祭を超えて、社会に可視化をもたらす重要な機能を果たしています。
しかし、予算や人員の制約、強固に残る伝統的価値観からくる理解不足、そして「顔が見える距離感」だからこそ高くなるアウティングリスクなど、課題は少なくありません。それでも、近年は日本全国の地方都市で地域に根ざしたイベントが増え、確実に広がりを見せています。2025年現在、北海道から沖縄まで30以上の地域でプライドイベントやパレードが開催されています。こうした取り組みの多くは、全国の主催団体が情報共有や相互支援を行うネットワーク「Japan Pride Network(JPN)」を通じてつながっています。都市部だけでなく地方都市でも、当事者の存在を可視化し、地域社会に理解を広げる動きが着実に広がっているのです。
3.都会から“持ち込む”のではなく、根ざす取り組みへ
地方のプライドイベントは、単なる「大都市の同イベントの輸入、縮小版」にとどまりません。地域に暮らす人々が「自分の愛する土地で、安心して暮らし・働き・生きる」ための取り組みとして独自の進化をとげています。ここで重要なのは、“根ざす”という視点です。
都市部のプライドイベントは、華やかで大規模なパレードや多くの出展ブースを擁するフェスティバルが特徴の一つです。こうしたイベントは社会的認知を高めるうえで大きな役割を果たしてきましたが、その形式をそのまま地方に持ち込んでも、必ずしも地域に受け入れられるわけではありません。なぜなら、地方にはその土地ならではの文化、価値観、コミュニティの距離感があるからです。
地方でイベントを開催する際に求められるのは、「外から来たイベント」ではなく、「まちの文化の一部」として根づくこと。地域の人々が「これは自分たちの取り組みだ」と感じられるようにすることが、持続可能性を左右します。そのためには、地域の歴史や風土に寄り添う工夫が不可欠でしょう。
融合事例①:街のイベントやお祭りに組み込む
多くの地方イベントでは、PRIDE関連の取り組みを既存の地域イベントやお祭りに組み込む方式が採用されています。たとえば、地元の秋祭りや商店街イベントの一角に「レインボーブース」を設け、LGBTQ+に関する情報発信や交流の場を提供したり、従来のパレードに一参加団体としてLGBTQ+関連の活動をしている団体が参加し、レインボーフラッグなどを掲げる試みです。こうした形なら、マンパワーや費用を節約できるだけでなく、地域住民が自然に立ち寄り、対話が生まれやすくなります。「特別なイベント」ではなく、「まちの日常の延長」としてPRIDEを位置づけることが、理解を広げる鍵になっているようです。
融合事例②:伝統文化とのコラボレーション
金沢プライドウィークでは、地元の工芸品や和菓子とコラボしたPRIDE関連の取り組みが話題になりました。地元の九谷焼の陶片を使用したレインボー箸置きを制作するワークショップを開催したり、代表やゲストがレインボカラーの加賀友禅の帯や着物を纏ったり、老舗和菓子店がレインボーカラーの上生菓子を販売したりする事例です。こうしたコラボは、地域の誇りである伝統文化と多様性の価値を結びつけ、「まちの魅力を再発見する機会」にもなります。観光客にもアピールできるため、地域経済への波及効果も期待できるでしょう。
4.都心と地方のPRIDE活動のちがい
規模と予算
都市部のプライドイベントは、スポンサー企業や自治体支援のもとで数万人規模のパレードを開催できる環境が整っています。たとえば「Tokyo Pride 2025」は来場者数約27万人を超え、協賛企業・団体も270社となりました(主催者発表)。
また、後述する大阪のイベントでは今年6万人超が参加し、福岡のイベントでも3万人超規模の来場者を目指しています。一方で、その他の多くの中小都市のプライドイベントは、です。予算も都心とは桁が違い、資金面や運営体制の多くがボランティア頼み。会場確保や行政手続きにおけるハードルもあり、「開催できるだけでも奇跡」と言われる地域も少なくありません。
しかし、この「小ささ」こそが、中小都市のプライドイベントの魅力でもあります。参加者同士が顔を合わせて語り合える距離の近さ、まち全体でつくる温かさがあるのです。
5.当事者の「見えやすさ」と表裏一体の「見えにくさ」
地方においては、人口の少なさ、地域社会の密接さ、そして「昔ながらの価値観」が残ることから、当事者が自分を表明しづらい状況が続いています。少しでも目立つとすぐに「○○さんちの孫の○○さんがあんなことをしている」と噂になる環境では「当事者であることを知られたら噂になる」「職場で不利になるかもしれない」と感じ、声を上げることをためらう人も多くいます。
一方で、これまでに行われてきたによると、手法や母集団によって割合に差はあるものの、例えば最近の電通調査では当事者割合は全国平均で約10%(10人に1人近く)と報告されています(出典:電通「LGBTQ+調査2023」)。つまりどのまちにも当事者はいるという事実があります。“見えない”ということは、“いない”のではなく、“見えにくい構造がある”ということ。だからこそ、「まちの中に確かに暮らしている人たち」の存在を感じられるようにするのが、地方プライドイベントの大切な役割なのです。
6.地域に根ざすために必要な「つなぐ力」と信頼の基盤
地方都市で活動するLGBTQ+当事者団体や支援団体は、限られた資金や人手の中で、まずは喫緊の課題に対応せざるを得ません。相談窓口の設置、当事者同士の交流の場の提供、緊急時の支援など、直接的なサポートは非常に重要です。
しかし、それだけでは「地域に根ざす」ための条件は十分ではありません。
本当に当事者が安心してその土地で暮らし、働き、生活を築くためには、当事者と非当事者を「つなぐ」ことが不可欠です。理解を広げるには、閉じた場だけでなく、一般市民に開かれた場が必要です。パレードや映画祭、トークイベントなどは、そのための有効な手段です。こうしたイベントは、当事者の存在を可視化し、地域社会に「ここにもいる」という実感をもたらします。
プライドイベントを単発に終わらせず、持続可能な取り組みとして地域に定着させるには重要な要素があります。それは信頼の基盤です。特に伝統的な価値観が根強い地方では、「誰がやっているのか」「どんな団体なのか」が非常に重視されるとも言われます。ここで、地元で信頼されている企業や、全国展開する大企業、自治体の後援が果たす役割は大きいのです。企業や自治体が後ろ盾となることで、イベントは「一部の人の活動」から「地域全体の取り組み」へと位置づけが変わり、様々な人を巻きこみやすくなります。
つまり、地方でのPRIDE活動を持続可能なものにするためには、当事者と非当事者をつなぐ開かれた場づくりと、地域に信頼されるバックボーンの構築という二つの要素が欠かせません。この両輪がそろって初めて、プライドイベントは「まちの文化の一部」として根づいていくのです。
- さっぽろレインボープライド
北海道・札幌市で毎年開催される北日本最大のLGBTQ+イベントです。1996年に「さっぽろレインボーマーチ」として始まり、全国のプライドパレードの草分け的存在でもあります。東京で一時期パレードが開催されていなかった時期にも、札幌では活動が途絶えることなく続けられ、国内のプライド文化をつなぎました。雪国ならではのあたたかい市民ボランティアや自治体・企業の協力も特徴で、まちぐるみで多様性を祝う雰囲気が根付いています。テレビ塔のレインボーライトアップも毎年お馴染みです。 - 金沢プライドウィーク
石川県金沢市で2021年から開催されており、伝統を重んじ保守的な価値観が根強い北陸の地で、「このまちでも共に生きる」を掲げています。地元出身の当事者の熱意から生まれ、能登半島地震後には被災地支援にも取り組むなど、地域課題と多様性を結びつけた活動が特徴です。上記のように地元の伝統工芸などとも積極的にコラボし、地域に根ざした共生の一歩を示しています。 - レインボーフェスタ!(大阪)
関西最大級のLGBTQ+イベント「レインボーフェスタ!」は、大阪らしい明るさと人情味にあふれるお祭りです。毎年10月に扇町公園で開催され、今年で11回目を迎えます。アカルクも毎年出展しており、今年は大阪・関西万博イヤーにあわせて、プライドパレードの過去・現在・未来をめぐる旅をテーマにした「アカルクパビリオン」を展開しました。
- ひろしまプライドパレード
広島では、2023年から地元のお祭りのパレードに一団体としてPRIDEを掲げ参加するかたちが取られてきましたが、単独でのプライドパレードとしては今年初めて開催されました。地元の広島銀行でサステナビリティ推進を担う社員がメインサポーターとなり、企業が率先して動いた点が大きな特徴です。人口減少や若者の転出など、地域が抱える課題と向き合いながら、「誰もがこのまちで働き、生きていける」社会を目指し、企業が地域の課題を解決しようと本気で取り組んだ好例と言えるでしょう。 - 九州レインボープライド(福岡)
九州最大級のLGBTQ+イベントで、2025年で11回目を迎えます。昨年は大雨で初日が中止となりましたが、今年は11月1日・2日に天神中央公園で開催予定です。パレードや模擬結婚式、ヒューマンライブラリーなど多彩な企画が展開されます。企業協賛も活発で、IKEAなどがキッズエリアに協力。初回から代表の三浦暢久さん(通称「のぶゑ」)が「誰もが自分らしくいられる空間づくり」を掲げ、地域と企業をつなぐ取り組みを続けています。オンライン中継も予定されています。
7.企業が果たせる役割
多くの全国展開している企業では、本社部門(人事・DEI推進機能)が都心に集中し、地方拠点まで十分に行き届いていないという現状があるようです。
「本社部門ではLGBTQ+に関する取り組みが進んできたけれど、支店や地方拠点まで手が回っていない」「地域とどうつながればいいか分からない」という声もよく聞きます。
しかし、企業が地方に根ざす活動を支える方法は、実は多様です。
- 地方拠点向けDEI研修の実施:地域特性(密な人間関係、伝統的価値観、地元企業ネットワーク)を踏まえたプログラム設計。
- との連携支援:地元のPRIDEやトークイベントに協賛・協力し、「まちの一員としての企業」であることを示す。
- 当事者との対話の場づくり:本社ではなく、地方拠点の社員が主役となる語りの場を支援する。
- 小さな始まりを支える:大きなパレードでなくてもよい。社内のランチトークや商店街との交流など、日常の延長にある活動を応援する。
こうした地道なサポートの積み重ねが、地域の信頼を生み、やがては企業ブランドそのものの「根ざし」にもつながるでしょう。
8.まとめ
地方のプライドイベントには、独自の意義や魅力が詰まっています。
そこには、地域に生きる当事者のリアルがあり、支える人の想いがあり、まちの未来があります。
仄かな火を灯し、その熱が地域に広がり、当事者とその周囲の人を照らしていく。
そんな循環を支えることこそ、私たち企業の役割ではないでしょうか。
地方拠点向けのDEI研修、地域イベントとの連携、当事者との対話の場づくりなど、現場に寄り添うサポートを検討したい場合は、ぜひご相談ください。
「根ざす」取り組みは、やがて全国のPRIDEの機運を育て、誰もが安心して暮らせる社会へとつながっていくでしょう。
執筆者:ししまる
IT中堅企業の人事としてDEI施策全般を主導する傍ら、社内外でLGBTQ +の支援活動にも従事。企業内担当者として、さらにイチ当事者としての目線からも、自分らしく働ける組織づくりについて発信します。