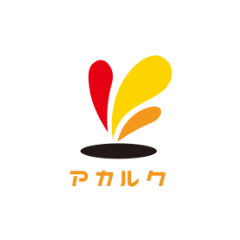近年、企業における多様性への取り組みが重要視されるなか、LGBTQ+への理解と適切な対応は、人事・採用担当者として持っておきたいスキルになりつつあります。
本記事では、採用におけるLGBTQ+当事者への配慮ある実施方法を、具体例を用いて解説します。コミュニケーションが限られている採用フローのなかで、どのような働きかけをすることが望ましいのか、ぜひご確認ください。
LGBTQ+の求職者を取り巻く環境
多くの企業がダイバーシティ推進の一環としてLGBTQ+に関する取組みを進めていますが、LGBTQ+の求職者を取り巻く環境は、未整備の部分が多く存在します。
就労時の困りごとについては以前のブログで紹介しましたが、困りごとを感じてるのは就労時だけではなく、就職・転職活動時にも多くの当事者が感じています。
2018年にLGBTの⼦どもの課題に取り組む認定NPO法⼈ReBitが行った調査(LGBTや性的マイノリティの就職活動における経験と就労支援の現状)では、LGB等の42.5%、トランスジェンダーの87.4%が選考時に困りごとを感じたと答えています。
人事や面接官、面接に際しての困りごとと回答した内容では
- 人事や面接官から、性的マイノリティでないことを前提とした質問や発言
- エントリーシートや履歴書に性別記載が必須
- 選考時、カミングアウトをすべきか・どの範囲にすべきか困った
- 人事や面接官が、性のあり方に関する知識や理解がなかった
といったものがありました。
特に「人事や面接官から、性的マイノリティでないことを前提とした質問や発言」についてはLGB等の方の約20%、「エントリーシートや履歴書に性別記載が必須」についてはトランスジェンダーの方の約45%が困りごととして回答しています。
企業の採用担当者として、LGBTQ+当事者が感じる採用時の困りごとにどのように向き合っていけば良いのか、どのような点に気をつけていくと良いのか、を次の章から解説していきます。
採用で気を付けるポイント
前述の調査結果にあるように、面接時だけでなく応募する際にも困りごとを感じる場面があります。
ここでは、応募時、面接時、面接後のそれぞれの場面において、LGBTQ+に配慮したうえで具体的に気を付けるポイントについて解説していきます。
エントリーシートや履歴書の性別欄
エントリーシートの性別欄への記載を必須としないことがポイントの1つです。
また、「備考欄」「その他自由記述」などの項目を設け、性別だけではなく、身体的や精神的な悩みや配慮、事前に相談したい事項、といった項目を1つ入れておくことで、相談もしやすく事前に伝えたい人は伝えやすくなります。
履歴書においても、応募者が性別欄が記載されていないものを使用したり、あえて性別を記入していない場合があることも知っておくと、その後の対応や配慮に気づけるポイントとなります。
エントリーシートや履歴書に記載された性別と外見が異なる場合でも、性を理由に応募者を評価することは適切ではありません。
書類選考の段階で、性別欄の記載や回答の有無が合否判定に影響を与えることのないよう、選考基準を明確にしておく必要があります。
ただし、業務の遂行上、一方の性でなければならない場合は、次のような性別制限が認められる可能性もあります。
- 表現の真実性等の要請から男女のいずれかのみに従事させることが必要な職務(芸能・芸術)
- 防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務(守衛・警備員など)
- 宗教上、風紀上、スポーツ競技の性質上など、必要性があると認められる職務
- 通常の業務を遂行するために性別関わりなく均等な機会や取扱いが難しい職務(坑内業務、危険有害業務、助産師など)
なお、これらの場合においても、その理由を応募者に説明をし理解を得ることも大切です。
出典:厚生労働省「男女均等な採用選考ルール」
話しやすい雰囲気づくり
面接時においては、話しやすい雰囲気づくりがポイントとなります。
普段行っている面接と変わらず、応募者と向き合うことを大切にしましょう。
その際に留意することは、採用担当者の発言が、勝手に決めつけた言葉になっていないか、シスジェンダーや異性愛を前提とした表現になっていないかを意識することです。
■勝手に決めつけた言葉の例
- 手術していないならトイレや制服は戸籍通りがいいですね
- ゲイの方なら結婚は考えていないですよね
- 性別適合手術を受ける時は有給を使われますよね
■異性愛者前提の言葉の例
- これから結婚や子どものご予定はありますか?
- 「うちの娘が学校で…」そういうことってありますよね?
- 奥様/旦那様は出張や残業を気にされますか?
ハラスメントにならないよう気をつけることも必要ですが、話しやすい雰囲気づくりを気にするがあまり、世間話に自身のプライベートに関する話題を踏まえ、異性愛者前提の内容や質問にならないよう気をつけましょう。
また、応募時や面接時に自身のセクシュアリティをカミングアウトされた場合、
- 全然普通ですよ
- 今の時代は全く気にしないですよ
- 差別や偏見はないですし、私は大丈夫ですよ
といった言葉も、過剰なアピールに聞こえてしまう場合があります。
もしLGBTQ+当事者かもしれないと思った場合は
- 皆さんにお聞きしていますが、何か働き方での希望や相談はありますか?
- 話せる範囲で話していただいて大丈夫ですよ
- 仕事をする上で何か心配な点はありますか?
といったさりげない言葉を伝えられると、本人は安心して話せる雰囲気をつくることができます。
応募者が自分を偽らず、ありのままに自己表現ができるよう、否定的な反応はせず、受容的な態度で耳を傾けましょう。
これにより、応募者は自分の能力や経験を十分にアピールすることができます。
社内での連携
次に、社内での連携の進め方が重要になります。
選考過程で応募者からカミングアウトを受けた場合、その情報を社内でどの範囲まで共有してよいか、本人に確認し同意を得ましょう。
また、自身のセクシュアリティに基づいた、働き方の希望についてなどのヒアリングした情報においても、社内のどの範囲まで共有して良いか、本人の意向を確認しておくことで入社まで円滑に進めることができます。
本人への同意の取り方の例として、まずは聞いた内容が選考判断に影響しない点を伝えます。
その上で、「お聞きした内容は〇〇の手続きの理由から次の面接官に共有しても差し支えありませんか?」「ご自身から伝えられますか?」と申し送りの同意を得ましょう。
特に、1次面接者から2次面接者への申し送りなど、アウティングが起きないよう情報をどの範囲まで共有していいのか、本人の同意を得ているのかを申し送り内容に含めるようにします。
面接結果をシステムに入力する際も、社内の誰が見ることができるのかを考慮し、本人の同意を得ていない場合はセクシュアリティのことは入力しないようにしましょう。
事前に同意を得ていなかった場合は、改めて本人へ同意を得た上で、その範囲内で共有します。
一方で、申し送りを受ける際に、もし情報の開示範囲が不明確だった場合は、
- 本人の同意を取れているのか
- どの範囲まで共有していいのか
を確認し、取れていない場合はこれ以上広めないように伝えることも重要です。
情報管理の重要性について、あらかじめ採用に携わる担当者間で認識のすり合わせをすることが最も大切です。
自社の採用条件を正しく把握
最後は、自社の採用条件を正しく把握しているか、です。
採用担当者は、自社の人権やダイバーシティ、LGBTQ+に関する方針や制度、福利厚生について、正確な知識や情報を持っておく必要があります。
応募者から「カミングアウトで合否や配属先に影響が出るか」「希望する性別で働けるか」「パートナーが福利厚生を利用できるか」といった質問を受けた際に、明確に回答ができるよう準備しましょう。
ただし、面接の本質は、応募者の職務適性を評価することです。そのため、セクシュアリティではなく、募集しているポジションや求める条件にフォーカスした質問と評価を行うことで、公平で適切な判断ができます。
企業としての対応
LGBTQ+の求職者が安心して面接を受けるためには、企業が誠実な対応を行うことが必要です。
面接官の理解と配慮が求められ、企業全体としてもLGBTQ+に関する適切な環境や制度を整備していくことが、企業の信頼性を高める要因となります。
採用担当者への教育
採用担当者によって対応の差異が生じないよう、事前にLGBTQ+について学ぶことができる研修の実施も1つの手段です。
研修を通じて、LGBTQ+に関する基本的な知識や事例を知り、自社の現状の採用フローや対応における課題を洗い出し、面接における留意点を把握しながら、実際の面接で活用していくことが大事です。社内の採用ガイドラインを作成することも、有効的な手段になります。
応募者への情報提供
LGBTQ+に関する企業の取り組みを、応募者に提供することも大切です。
面接の時間内で、応募者が会社のLGBTQ+に関する施策について、積極的に質問することは難しいでしょう。
LGBTQ+に関する取組みを行っている場合は、HPやパンフレットに掲載することで、応募者が事前に情報を集めたうえで面接に臨むことができます。
他にも、募集要項等に性的指向・性自認・性表現に関する差別を行わないことを明記したり、企業のLGBTQ+に関する施策が記載された資料やウェブサイトを提供することも効果的です。
また、LGBTQ+の求職者の応募基準が、「PRIDE指標」といった外部指標を獲得している企業かどうかという場合もあります。
※PRIDE指標とは、「work with Pride」によるLGBTQ+に配慮した取り組みを評価する指標です。PRIDE指標を獲得することは求職者側の応募軸になるだけでなく、社内でのLGBTQ+に関する取り組みを見直す良い機会にもなります。
出典:work with Pride PRIDE指標
自社のHPや説明会だけでなく、外部指標も活用しながらその取り組みを発信していくことで、多様な人が働きたいと思える企業になり得ますし、応募者が安心して採用に臨めるよう配慮することができます。
まとめ
今回は、採用担当者向けにLGBTQ+に配慮した面接の具体例をご紹介しました。
採用担当者は、求職者と企業をつなぐ重要な役割を担っています。採用担当者がLGBTQ+に関する理解を深め、面接や職場環境で適切な配慮を行うことが、多様な人材の活躍を促進することにつながっていきます。
株式会社はアカルクは、ダイバーシティ推進のための取り組みをはじめ、LGBTQ+の方がどのような事に配慮が必要なのか、多様性を意識した採用担当者に特化した研修から、入社前、入社後のガイドラインの策定、制度構築、運用を一気通貫で行う人事コンサルティング、キャリア支援といったプロデュース事業を展開しています。
「LGBTQ+について取り組みたいけれど、どんなことから始めたらいいのか分からない」といったご相談や、ピンポイントで「研修」や「外部相談窓口の設置」といったご依頼でも幅広くお受けしています。施策実施・制度策定までの、社内合意形成のプレゼンのお手伝いなども手掛けています。
今回の記事で取り上げたLGBTQ+の求職者への配慮した面接の進め方について、様々な課題に関する漠然とした不安や具体的な対策についてもご提案が可能です。
まずは相談でも構いませんのでいつでもお声掛けください。