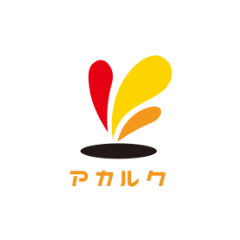誰もが安心して楽しめるイベントづくりの先に目指すもの
取り組みとその背景
堀川:最初に2024 年に制作された「イベントにおけるLGBTQ+ ハンドブック」について、その内容と制作背景について教えていただけますか?
佐々木:まず始めに、LGBTQ +というテーマで制度を考えてみないかという話が人事総務部の中でありました。ただ、その制度をつくるにあたり、社員のLGBTQ +に関する知識や感じ方など、生の声を聞いてみることが先ではないかという話になりました。そこから、堀川さんにご協力いただき、LGBTQ +研修を開催することにしました。私個人としても、それまではLGBTQ +に対して他人事というか、遠い存在というイメージでした。研修では、当事者の堀川さんからイベント現場における注意点、苦労された話などを直接聞くことができ、自分に身近なものだと感じられたすごく良い機会でした。研修後のアンケートを見るとこれまでの他の研修よりもすごく積極的・前向きな意見が多く、イベント現場でも参加者やアルバイトスタッフ、主催者の方も一緒に使えるハンドブックをつくってみてはどうかという意見があがり、研修の次の段階としてハンドブックの制作に取り掛かりました。
古田:もともと、パートナーシップ制度を社内に導入したいと考えていたときに、なかなか上手くいかず、堀川さんに相談させていただいたことがきっか
けでした。その後、堀川さんよりイベント現場におけるハンドブックはこれまでおそらくないから、作してみてはとご提案いただき、「それは、いいな」と、経営層も乗り気になってくれるのではないかと思い、制作が決まりました。
堀川:研修での取り組みについて、オープンに参加者を募った際に、何か工夫などはされましたか?
佐々木:特に工夫はしていません。今までのセレスポの社内研修は対象者を決めて、半ば強制的な形で研修を行っていました。今回のLGBTQ +研修では、はじめて参加者募集型を導入しました。結果として、LGBTQ +に関する研修では40 〜50 名程度集まり、アーカイブを含めると100 名程度が参加しました。今までの研修でオープン参加型のものがなかったので、強制感がなかったせいか、気楽に参加できたのではないかと思います。
ハンドブックについて
堀川:「イベントにおけるLGBTQ+ ハンドブック」にはかなり反応があったと伺いましたが、実際どれくらいのダウンロード数がありましたか?
越川:ハンドブックを公開した月に400 を超えるダウンロードがあり、現在では500 を超えています。
堀川:それはかなりの反響ですね!ダウンロード以外での反響もありましたか?
佐々木:いくつかの自治体様から問い合わせがありました。イベントを開催するので、スタッフに共有していいか、他の課にも共有していいかなどとお話
をいただきました。
古田:他にも、イベントの現場で使うスタッフ向けの教育資料を、ハンドブックの内容をもとにアレンジしたいので許可をいただきたいという話はありま
した。
越川:ある自治体では、昼休みに行っている自主的な勉強会で紹介したいと言われました。
堀川:自治体からの声が多かったのですか?
越川:自治体に限らず、広くイベントに関わる方からの要望もありましたね。対外的だけでなく社内の変化でも、前向きに受け止められる人が増えたので
はないかと思います。これまで、LGBTQ +についてなかなか積極的には取組めていなかったですが、それこそ埼玉県との取り組み(性の多様性に関する
企業を対象とした取組)にエントリーしたのは大きな前向きな一歩かなとは思います。

座談会について
堀川:ハンドブックに掲載された「座談会」は他の当事者の方もお招きし、クロストーク形式で開催されていましたが、その形式をとった理由はあります
か?
古田:実際に生の声を聞きたいというのが一番の思いとしてありました。一番はじめに教育研修をやった後のアンケート結果から、興味ありそうな社員を
選抜し、ハンドブックを制作するメンバーを募りました。とはいえ私たちもまだまだ知識以前に、実際に当事者の方がどういった点で困っているのかわか
らない状況だったため、まずはお話を聞いてみようと、座談会を開催することになりました。
堀川:座談会での話をハンドブックに反映させるためグラレコ※を使うなど、非常に一体感ある場だったのが印象的でした。普段から社内の啓発の中でも、そうしたエッセンスは入れているのでしょうか?
佐々木:あのような座談会はこれまでにあまりない形でしたが、私自身もあの場で一体感を感じていました。地方からも積極的な意見を持っている社員が
集まり、メンバーが集中してお話を聞いたり意見を交換できたのは非常に貴重な経験だったなと思います。それぐらい他の研修もやれるといいんですけれ
ども(笑)。
越川:私たちを含めて、この分野に詳しい人がおらず、みんな同一線上に立ったというのが良かったのかもしれません。詳しい人がいると、そちらの意見
によっていっちゃうことがあるので。あと、社内ではない場所での開催がさらに良かった点ですね(笑)。
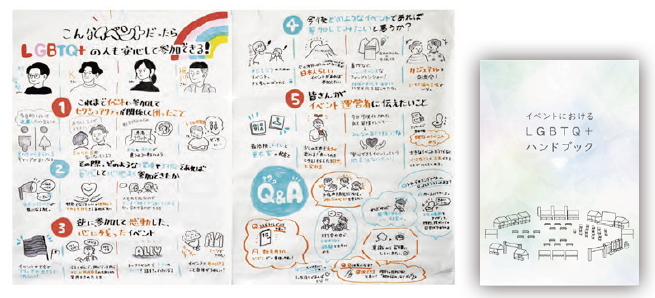
▲「イベントにおけるLGBTQ+ ハンドブック」とグラフィックレコーディング
※グラフィックレコーディング(グラレコ)とは、会議やプレゼンの内容を絵や図形などのグラフィックを用いてまとめる手法のこと
埼玉県との取組みについて
堀川:埼玉県様の取り組みについてさらに伺いたいのですが、そうした取り組みをやっていきたいというのは社内の方から声が上がったのでしょうか?
佐々木:ハンドブック制作メンバーの一人の目に留まったのがきっかけです。これまでLGBTQ +に関する事業には取組んでいませんでしたが、ハンドブックを制作したからこそ、その経験を活かしてやってみようとなりました。タイミングもバッチリだったので。
堀川:そこからだったんですね!その取り組みをやったことによってさらに社内での意識も変わりましたか?
佐々木:さいたま支店がそのようにチャレンジしているのは、いろいろな形で全国の支店・営業所に発信されており、そこから、各自治体が行っている
LGBTQ +関連の推奨企業認定(LGBTQ +フレンドリー認定企業)へ登録するのをうちでもできるのではないかと、人事総務部に相談する部署は増えて
います。
取り組みのバランス
堀川:社内施策だけで終わるケースもよくありますが、セレスポ様の場合は社内外の取り組みを社員さんの声を聴きながら同時にバランス良く進めてい
らっしゃると感じました。そのバランスは意識的に狙われたのですか?
佐々木:やっぱり、ベースが社員のアンケートから意見を拾ったことからスタートしていることが大きいと思います。
越川:企業がLGBTQ +など社会課題に向き合うことは、なかなか中小企業では難しく、余裕のある組織の取り組みになりがちかと思います。ただ、私た
ちのようなイベント事業だと当然、当事者の方が参加され、目に見えて直面している課題・事実ですので、社員も自分事として捉えやすいのかもしれませ
ん。現在、社内で当事者であることを公表している人はいないのですが、公表していないだけで社内にもいらっしゃるのかもしれませんし、イベントでは、参加者や登壇者の方が当事者という場合があるので、想像しやすいのが良かったのではないかと思います。
堀川:確かにイベントの場合は、参加する側、企画する側も直接関係しやすい分、身近に考えやすく取り組みに反映しやすいことも納得です。
アカルクを選んだ理由
堀川:多岐にわたり御社とご一緒させてもらっていますが、今回アカルクと一緒に取り組みさせていただくきっかけはありましたか?
越川:何人か当事者の方を知っていましたが、研修を実施するにあたって他の候補者を考えたときに、信頼している知人から堀川さんを紹介していただき
ました。何人か候補者がいた中で一番ビジネスの視点でもフラットで偏っていない方がいいなと思い、堀川さんにお願いしました。
佐々木:私自身は初めての企業様との取引だったので、独特な雰囲気をお持ちの方なのかと想像していましたが、一番最初に堀川さんにお会いしてマイル
ドな(まろやかな)印象を受け、構えなくていいんだと安心できました。

これまでの効果
堀川:これまで様々なお取り組みを実施された中で効果や結果は感じられますか?
佐々木:LGBTQ +の取り組みをきっかけに、これまで男女で分けられていた規定・行動基準を見直したり、社内の発信物の名簿や新入社員の番号順を性
別で分けることなくあいうえお順に変更したり、私たちの感覚に少しずつ染み込んで、通常の業務にも反映されてきているなと実感しています。
古田:4 月に事実婚を含めたファミリーシップ制度の導入まで進めることができたことが結果につながったと思います。制度を導入するにもゼロからで
は難しいと思うので、研修やハンドブックの制作によって、LGBTQ +の取り組みが社内に少なからず周知され、社員にもあまり唐突感なく社内制度の導
入を受け入れてもらえるのかなと思います。
越川:4 月に制度を導入して、すぐに申請はないかもしれないですが、月日か経って申請される方がいたときに、その人がこの会社は安心できる場所だっ
たんだなと思ってもらえるといいですよね。それが、効果じゃないでしょうか。特別な意識を持たなくなってきているというのが大きいかと思います。
取り組みの先に目指すもの
この先、どのような制度作りを目指されているのか教えてください。
古田:今進めているのが、事実婚を含めたファミリーシップ制度です。内容としては、同性カップル、そのお子さんを含めたファミリー、また事実婚の方も、今までは使えなかった特別休暇と結婚のお祝い金などを使えるようにしようというものです。各自治体のパートナーシップ制度やファミリーシップ制度に登録された方が、その証明書を出していただいたり、事実婚の方は住民票を出していただくことで、そうした福利厚生制度が利用できることを進めています。他には、ハンドブックも、バージョンアップしたいですね。現場のメンバーも、取り組みをここで終わらせず、さらに広げていきたいと思っているようですね。
佐々木:制度導入と同時期に社内専門窓口の設置も行うため、専門の当事者の方と一緒にケアをしていくというメッセージを従業員に伝えられたらいいな
と思っています。
越川:現在、当事者の方が顕在化していないというのが会社の状況ですが、実際採用面接では当事者であることをその場でカミングアウトする学生も増え
たので、今後はカミングアウトされた当事者の社員も入社されてくるかと思います。取り組みを続けることで、今後入社される方も、現在社内に生きづら
さを感じている人も、何年か経ってその人がセレスポで良かったなと思ってもらえたら嬉しいですし、取り組みを行っている他の会社の人事や総務の方た
ちとも繋がれたらと思っています。
対談者紹介

越川 延明
株式会社セレスポ
人事総務部長

古田 盟代
株式会社セレスポ
人事総務課長

佐々木 悠子
株式会社セレスポ
人事総務課長

堀川 歩
株式会社アカルク
代表取締役社長