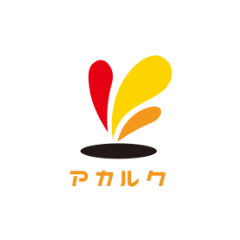2025年10月21日、自由民主党の高市早苗氏が第104代内閣総理大臣に就任しました。
日本初の女性総理誕生に、国内外から祝福の声があがる一方で、女性ならではの「ジェンダー施策」にも注目が集まっています。
実際に高市氏は総務大臣時代、結婚後も旧姓を利用して働き続けられるよう制度を整備するなど、結婚による不利益を減らす取り組みや、男女の機会平等の実現に向けた施策を進めてきました。
その一方で、これまで性的マイノリティの権利保障に対しては慎重な姿勢を示してきた経緯があり、当事者をはじめ多くの人が今後の政策動向を注視しています。
高市新政権の発足により、日本のジェンダー平等はどのように変わるのか。これまでの政策の流れと今後の展望、そして企業に求められる対応について考えていきます。
LGBT理解増進法(旧LGBT法案)と外圧から見る日本のジェンダー平等
日本のジェンダー平等を語るうえで欠かせないのが、「LGBT理解増進法(旧LGBT法案)」と「外圧」です。
ここでは、この2点について整理していきます。
LGBT理解増進法案(旧LGBT法案)の紆余曲折
「LGBT理解増進法」とは、LGBTQ+に関する正しい知識を広め、国民の理解を深めることを目的とした法律のこと。正式名称は、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」です。
同法案は当初、2021年の東京オリンピック・パラリンピック開催前の成立を目指していました。
しかし、自民党内の保守派を中心に反対の声が上がり、法案提出は見送られることに。反対理由の1つが、「“差別”という文言の定義が曖昧で、恣意的な訴訟が増える懸念がある」というものです。
その後、修正を経て2023年6月にようやく成立。しかし、その際には文言が大きく変更され、「差別は許されない」という表現が「不当な差別はあってはならない」へと修正されました。
| 当初案 | 成立案 | |
|---|---|---|
| 差別の表現 | 差別は許されない | 不当な差別はあってはならない |
| 表記 | 性同一性 | ジェンダーアイデンティティ |
| 合意主体 | 与野党の超党派議連 | 与党主導の修正案 |
| 評価 | 当事者から支持多数 | 当事者・支援団体から後退と批判 |
もともと同法案は、超党派の議員連盟によってまとめられた合意案がベースでした。
しかし、自民党内では「同性婚の法制化につながるのではないか」「家族制度や伝統的価値観が揺らぐのではないか」といった懸念の声が根強く、結果として与党主導の修正が加えられる形となりました。
こうした経緯からも、政府与党のLGBTQ+に対しての慎重な姿勢が伝わります。
国際社会からの視線と政策への影響
国際社会からの視線も、今後の日本のジェンダー平等を考えるうえで欠かせない要素です。
LGBTQ+に関する法整備において「日本は欧米を中心とした先進諸国と比べて後れを取っている」と、これまで何度も国際社会から指摘されてきました。
実際に2021年には、「Human Rights Watch」や「アムネスティ・インターナショナル」などの国際人権団体から、差別禁止法の制定を求める要請が日本政府に対して出されました。
欧米で進む多様性と平等への取り組み
日本と比べて特に欧米諸国では、以下のような施策がすでに実現・進行しています。
- 同性婚の合法化
- 雇用・教育・公共サービスにおける差別禁止法の整備
- トランスジェンダーへの医療アクセスの確保
もっとも、欧米諸国のすべてが常に前進しているわけではありません。近年のアメリカでは、トランプ政権下でLGBTQ+やジェンダー平等をめぐる取り組みが、以下のように一部後退する流れも見られています。
- 性別定義の変更:性別を「生物学的な男女のみ」と規定
- DEI(多様性・公平性・包摂)プログラムの廃止:「差別的優遇」として、連邦機関や企業の多様性・公平性・包摂(DEI)推進プログラムを廃止・停止
- 女子スポーツへの参加制限:トランスジェンダー女性の女子競技(学校・大学含む)への参加を禁止する大統領令に署名
とはいえ、ジェンダーや多様性をめぐる政策環境において、日本が先進諸国と比べて遅れを取っていることは否めません。
国際的な潮流を踏まえつつ、日本社会に適した制度や意識改革をどう進めていくかが問われているのが現状です。
G7サミットが転機に:広島での議長国の責任

画像出典:G7 HIROSHIMA2023
特に注目すべきは、2023年のG7広島サミットです。日本が議長国を務める立場だったこともあり、世界中からこれまで以上に厳しい目が向けられることに。
実際、このタイミングで以下のような批判が相次ぎました。
- 「G7の中で唯一、LGBTQ差別禁止法が存在しない国」
- 「同性婚すら認められていない唯一の先進国」
こうした国際的な批判に対し、日本政府内でも「最低限の法整備は必要ではないか」という意識が広まりました。これを機に、LGBT理解増進法の国会提出・可決へとつながったとも言われています。
自民党政権は長年、LGBTQ+やジェンダー施策に対して慎重姿勢を取ってきました。しかし、国際的な圧力が転機となり、徐々に政策に変化が生まれつつあります。
高市新総裁のスタンスから見る今後のジェンダー政策
こうした流れの中で、ジェンダー政策について高市新総裁率いる政権が今後どのような立場を取るのか。引き続き注目が集まっているところです。
ここでは、これまでの発言や立場から、高市氏のジェンダー/LGBTQ+施策に対するスタンスを見ていきます。
LGBT法案に対する姿勢は「非常に慎重」
出典:立憲民主党 国会情報
2023年2月9日の衆院予算委員会において高市氏は、先述のLGBT理解増進法について「文言について十分な調整が必要」と述べるなど、法案の内容そのものに慎重な姿勢を示しています。
いわゆるLGBT法案については、元の自民・公明案のままなら私も賛成出来ないと考えていました。維新・国民との修正協議により、民間団体の活動促進は削除され、全ての国民の安心の為に政府が指針を策定する規定が追加され、保守系識者から指摘されていた懸念点は一定程度、解消されたと判断しました。
— 高市早苗 (@takaichi_sanae) June 18, 2023
実際、LGBT理解増進法の修正について、高市氏は自身のX(旧Twitter)で「元の自民・公明案のままなら賛成できなかった」と投稿しました。
投稿の中では「民間団体の活動促進が削除され、政府が指針を策定する規定が追加されたことで、懸念が一定程度解消された」とも述べています。
この投稿からは、「活動が行きすぎた先にある訴訟リスク」への不安が取り除かれ、安心したという意図が読み取れます。
つまり高市氏は、LGBT当事者への理解促進という理念自体を否定しているわけではないものの、「社会の調和」や「国民全体の安心」を重視する立場から、法案の内容や表現には細心の注意を払う姿勢を貫いていることがうかがえます。
同性婚に対しては「基本的に反対」
また、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」と定める憲法24条についても「難しい問題」と述べ、同性婚の法制化についても慎重な姿勢をとっています。
出典:ニコニコニュース 【自民党総裁選2025】総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会(49:47~)
実際に2025年9月に行われた「N高グループ・N中等部」の生徒との「日本の未来討論会」では、「基本的には同性婚に反対の立場」と発言しています。
さらに、憲法24条(「婚姻は両性の合意のみに基づく」)にも言及しつつ、「非常に難しい問題」と述べるなど、法改正には否定的な見解を示しました。
一方で、同性のパートナーシップについては一定の理解を示す姿勢も見られます。ただし、法制度としての同性婚やLGBT差別禁止法といった政策レベルの整備には後ろ向きであることが読み取れます。
今後の政策で懸念されることと注目すべき動き
これまでの高市氏のスタンスから、新政権のもとではジェンダー政策に対する動きは慎重・保守的なものとなる可能性が高いと見られています。
特に、同性婚の法制化やパートナーシップ制度の法的保障、LGBTQ差別禁止法の制定など、これまで議論されてきた制度的な整備については、前向きな進展は限定的になる可能性もあります。
現行の「LGBT理解増進法」は、あくまで「不当な差別はあってはならない」と理念を掲げたもの。罰則や強制力のない努力義務にとどまっています。
高市政権下でも、こうした“理念先行・実務後回し”の傾向が続く懸念は否めません。
同性婚訴訟の行方と政権の対応
全国5つの地裁(札幌・東京・名古屋・大阪・福岡)で進んできた「結婚の自由をすべての人に」訴訟。
同性婚を認めない現行制度が憲法違反かどうかを問う裁判は、いよいよ2026年に最高裁判断が出る見通しです。
高等裁判所ではすでにすべての判決で「違憲」または「違憲状態」との判断が出ており、最高裁でも違憲とされる可能性は十分あります。
しかし、仮に違憲判決が出ても、最終的な法整備を行うのは国会です。高市氏や自民党が引き続き慎重な姿勢を取る場合、最高裁が違憲と認定しても、同性婚の制度化が進まないという事態も想定されます。
国際社会の視線と構造的変化の兆し
一方で、日本政府がいくら慎重姿勢を取っていたとしても、国際社会からの視線や圧力はますます強まっています。
G7諸国の中で唯一、LGBTQ差別禁止法が存在しない日本。同性婚も法制化されていないことから、海外メディアや人権団体からは「対応が遅れている国」と見られてきました。
こうした批判を背景に「LGBT理解増進法」が成立する動きが加速したように、国際的なイベントや圧力が、国内法整備の引き金になる可能性もあります。
さらに、全国でおよそ530以上の自治体が同性パートナーシップ制度を導入し、世論調査でも同性婚への賛成が過半数を超えるなど、草の根レベルでの変化が着実に進んでいるのも事実です。
たとえ政権が慎重派であったとしても、こうした「構造的な追い風」を前に、大きな流れを止めることは難しいでしょう。今後5年の間に、日本のLGBTQ+政策が歴史的な転換点を迎える可能性は、十分にあります
企業に求められる変化と主体的な取り組み
新政権の発足により、LGBTQ+に関する社会環境がどう変わっていくのか。現時点ではまだ不透明であり、むしろ制度的な後退や停滞への懸念も拭えません。
だからこそ今、企業が自律的に多様性への取り組みを進める姿勢が、これまで以上に重要になっています。
制度整備の遅れが現場の迷いや混乱を招く中でも、企業が主体的に「誰もが安心して働ける環境づくり」を目指すことは、信頼やブランド価値の向上にもつながります。
ここでは、特に注目すべき3つの取り組みを紹介します
LGBTQ+施策の明文化と開示
現在、多くの企業が「D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)」を掲げていますが、実際の取り組みが不透明なケースも少なくありません。
今後は、対外的な信頼を得るうえでも、LGBTQ+に関する施策の可視化・透明性が強く求められます。
例えば、以下のような情報の開示が推奨されます。
- LGBTQ+に関する行動指針・社内ポリシーの明文化と公開
- ハラスメント防止の社内規程(SOGIハラ対策など)
- 多様な家族形態を尊重した福利厚生(同性パートナーシップ制度、休暇制度など)
こうした方針は、社外に対してだけでなく、社内従業員にとっても安心材料になります。
社内教育・研修の強化
制度だけでは、差別や無理解を完全に防ぐことはできません。特に管理職や人事担当者など、影響力のある立場の人々に対しては、継続的な教育機会が必要です。
近年問題視されている「SOGIハラ(性的指向・性自認に関するハラスメント)」などは、知識不足や悪意のない無理解によって起こりますが、実際問題「知らなかった」では済まされません。
LGBTQ+当事者の声を交えた対話型研修や無意識のバイアスに気づくワークショップなどを行い、一度きりで終わらせず、定期的にアップデートしていく仕組みが重要です。
社外への姿勢表明とブランド戦略
さらに、企業としての姿勢を社外に発信することも大切な取り組みです。
LGBTQ+関連のイベント協賛、レインボーキャンペーンの実施、企業HPでのメッセージ発信などを行うことで、企業ブランディングの強化にもつながります。
これは単なる「アピール」ではなく、価値観や社会課題への意識を重視するZ世代やミレニアル世代に対する採用面でのアドバンテージにもなります。
一方で、発信内容が実態と伴わない場合は「ピンクウォッシュ」や「レインボーウォッシュ」(※)として批判を受けることもあります。
形だけの発信に終わらせないためにも、継続的かつ誠実な姿勢が求められます。
※企業が社会的メッセージを打ち出しながら、実際には十分な取り組みを行っていない状態
制度と企業、両輪の前進が社会を動かす
LGBTQ+を取り巻く環境整備は、「政府によるトップダウンの制度整備」と「企業によるボトムアップの実践」の両輪がかみ合ってこそ、社会全体で前進していきます。
今後数年でどのような制度が実現するかは不透明でも、企業や自治体が率先して行動を示すことで、社会のムードは着実に変わっていくでしょう。
アカルクは、LGBTQ+当事者の声と企業・自治体の現場をつなぐ専門家集団として、情報発信・制度設計・現場支援を行っています。「自分たちにできることから始めたい」と思ったとき、その一歩を支えるのが私たちの役割です。
施策設計に関するご相談や、社内外へのアピール方法など、何から始めればいいか迷っている企業・自治体の方は、ぜひアカルクまでご相談ください。
執筆者:佐藤ひより
大手メーカーの海外営業職を経験後、2018年にライターとして独立。フリーランスとして多様な価値観や働き方に触れる中で、「一人ひとりが自分らしく生きられる社会」に関心を持つように。現在は、キャリア・ビジネス・ライフスタイル分野を中心とした記事制作に携わっています。