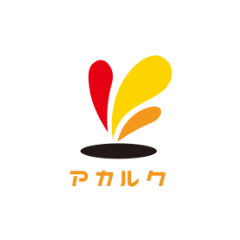こんにちは、学生インターンの齋藤です!
大学生の多くは、どのような授業を受けているのでしょうか?文系では社会学系の授業が人気ですが、その中でもジェンダーやセクシュアリティ、LGBTQ+やクィア理論に関する授業は、教養科目の一つとして多くの学生が履修しています。こうした授業を通じてLGBTQ+などに興味を持つ学生も少なくありません。
私自身は大学でクィア・スタディーズを専攻しています。クィア・スタディーズはもともと性的マイノリティの社会運動に関する議論から生まれました。今は、主にジェンダーやセクシュアリティに関する「当たり前」や「普通」を問い直す学問で、どんな人が、どんな仕組みの中で生きやすく、あるいは生きにくくなっているのかを考える分野です。
しかし、このような学びをどのように社会に活かせられるのか、なかなかイメージできない人も多いのではないでしょうか?私も実はその一人でした。
クィア・スタディーズが成し遂げようとしていることと、アカルクの誰もが自分らしく働ける社会を作るというミッションが似ていると思い、大学での学びをがどのように現場とつながるのかを、インターンを通じて探ってみることにしました。
本記事では、実際にアカルクでのインターンの経験を通じて、果たして大学で学ぶような理論を仕事にも持ち込んで使えるか、そしてどのようにして使えるのかを紹介していきます。
理論を持ち込むことは難しい?
インターンを始めた当初、私は「大学で学んだ理論を現場で活かせるはず」と思っていました。
実際には、業務の中心はミーティングや研修への同行、イベントの運営のサポート等で、理論を直接扱う場面はほとんどありませんでした。
大学で学ぶクィア理論やジェンダー研究は専門的、かつ抽象的です。例えば、「性の二元論を問い直す」ことや、「社会的構築物としての性」といった内容を学びます。
しかし、これらを直接的に「ビジネスの場」で使うとなると難しい部分があります。現場では分かりやすさと、すぐに実践できるかどうかが重視されるからです。アカルクが支援する企業の多くは、まず従業員の間で「LGBTQ+とは何か」「どのように接すればいいのか」といった基礎的な理解を促している段階にあります。私自身も、面談に同席させていただく中で、まだ制度や言葉の履修から始めている企業が多いことを実感しました。
社会全体におけるLGBTQ+理解の広まりのスピードから考えれば、これは自然な流れとも言えます。「LGBTQ+」という言葉が社会に浸透し始めたのは2010年代頃に入ってからであり、企業が性的マイノリティへの配慮を本格的に考えるようになってから、まだ10年程しか経っていません。
その意味で、企業にとってはまず「正しい理解を共有する」ことがスタートラインになっています。
理論を現場の文脈に「翻訳」する
では、学んだ理論を全く使えないということなのでしょうか?
もちろん、そんなことはないです。
そもそも現場で理論をそのまま使えないのは、そもそも学問と実務の目的が異なるからでです。
大学では、「社会の構造を批判的に分析する」ことが重視されますが、一方企業では「人が安心して働ける仕組みを作る」ことが求められます。これらの目的で重なる部分はもちろんあります。しかし、その大部分において理論をそのまま当てはめるのではなく、実務の文脈に合わせて「翻訳」することが求められます。
だから理論を部分的に利用したり、もしくは理論そのものではなく、その理論を考える上での姿勢を常に持ち込むことが重要です。
クィア理論やジェンダー研究は抽象的だからこそ、さまざまな場面に応用できる柔軟さがあるとも言えます。
たとえば、クィア理論で重視される概念に「インターセクショナリティ(交差性)」があります。これは、一人の人間が複数の属性(e.g. LGBTQ+の当事者であり、女性であり、障がい者である)を持つときに、それらの属性が交差することで新たな困難や差別が生じることを指す考え方です。
この視点は、企業の制度を設ける上で非常に重要です。
たとえば、企業が家族手当や育児休暇制度を設計するとき、「異性愛・既婚・子育て中」という特定の前提で制度を作ってしまうと、同性パートナーシップやシングルの従業員が利用できないケースもあります。インターセクショナリティを元に重層的な課題と向き合えば、誰もが制度の「対象外」にならない職場づくりにつながっていきます。
このようにクィア理論を全ての物に導入しなくとも、所々で使うことができます。
また、クィア理論やジェンダー研究の醍醐味は「“普通”を疑う」ことにあります。この姿勢をインターンをやる上で常に持つだけでも、学びを応用できていると言えます。
たとえば、ミーティングに同行する時に、LGBTQ+やジェンダーに関してどのようなランゲージを使っているのかを気に留めることや、逆に誤解を生むような言葉遣いなっていないか注意を払うことも、小さいことではありますが、大学での学びを現場で活かす一つの方法です。
また、重要な姿勢の一つに、「前提を問い直す」というものがあります。たとえば、イベントを企画する際に、そのイベントに「誰が参加できるのか、誰が参加できないのか」「誰を想定して作っているのか」を考えることもクィア的なまなざしの実践です。実際にアカルクは毎年10月に大阪で行われるレインボーフェスタというイベントに出展しますが、そこで出展の対象になりにくい子供もが楽しめる企画を出すようにしています。
こうした問いを持ち続ける姿勢そのものが、理論を現場に息づかせる実践と言えるでしょうか。
■理論と実務のかけ橋
ジェンダーやセクシュアリティに関する学びは、すぐに職場や実務の場で役に立つものではないかもしれません。
しかし、その学びは社会をより柔軟に、そして共感の眼差しを持って見つめるための思考トレーニングでもあります。
理論と実務の間にある「距離」を感じつつも、その間を考え続けることはこれから社会に出ていく学生にとっても、多様性を推進していく企業にとっても、重要なことではないでしょうか。
大学での学びと企業での実践は、しばしば「理論と現場」という二項対立のように語られますが、両者は断絶しているわけではなく、互いに学び合う関係にあります。理論と実務の橋渡しは、個人の努力だけではなく、組織がともに学び続ける姿勢の中でこそ可能になると私は思っています。
実際にインターンを通して感じたのは、理論は社会課題への「答え」ではなく、「問いを立てるためのツール」なのだということです。現場で出会う課題は理想的な社会を前提にした理論だけでは解けないことも多くあります。
理想的ではない社会において、どのような制度がみんなにとって生きやすいようになるのかを考え続ける必要があると感じました。
理論はあくまでも出発点であり、終点ではありません。理想と現実の間で揺れ、行き来し続ける姿勢が、生きやすい社会を作る第一歩につながると思います。今後、私は大学を経ても社会の中にある「当たり前」を問い直す姿勢を持ち続けたいです。そして、インターンで得た「現場に耳を傾ける」という姿勢を中心に、LGBTQ+の人をはじめ、さまざまな人が生きやすい社会になるように、制度や文化を変えていく取り組みに関わっていきたいと思います。
書き手紹介
学生インターン 齋藤
現在、大学2年生で、クィア・スタディーズやジェンダー研究を専攻。
大学での学びと実際の現場の違いを見たいと思い、アカルクに入社。