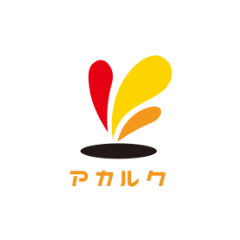友人同士の何気ない会話、職場、飲み会といった場面で、誰かの個人的な情報を話に出したことはありませんか?
その情報があなたにとって深刻な内容でなかったとしても、話題に出す前に、踏みとどまる必要があるかもしれません。なぜなら、それが「アウティング」に該当する可能性があるためです。
本記事では、日常生活で起こりやすいアウティングについて詳しく解説します。
誰もがアウティングをする側にも、される側にもなる可能性があります。また、あなたの何気ない一言が、誰かの人生を大きく変えてしまう可能性もあります。
本記事を通じ、アウティングについて考えるきっかけにしていただけたらと思います。
アウティングとは
アウティングとは、英語の「out」(外に出す)から派生した言葉です。
1980年代のアメリカで、著名人のセクシュアリティを本人の意思に反して公表する行為を指す言葉として使われ始め、「カミングアウト(Coming out)」の強制的な方法として認識されていました。
現在では性的指向や性自認に限らず、「不当な暴露による人権侵害」という、プライバシーに関わる大きな問題を表す用語として使われています。
アウティングは以下のような個人情報を、本人の同意なく第三者に暴露する行為全般を指します。
- セクシュアリティ(性的指向・性自認)
- 病歴や健康状態
- 家族構成や家庭環境
- 経済状況
- 出身地や国籍
- 障害の有無
- 職歴や学歴
- 交友関係
アウティングとカミングアウトの違い
アウティングとカミングアウトの違いは、「自己決定権の有無」です。
カミングアウトは以下のように、本人が自らの意思で、自身に関する情報を他者に打ち明ける行為です。
- 本人が主体的に選択できる
- 開示する相手を自分で選べる
- タイミングを自分で決められる
- 開示する情報の範囲をコントロールできる
- 自己肯定や周囲との信頼関係構築につながる可能性がある
一方のアウティングは、本人の意思に反して、第三者が情報を暴露する行為です。
- 本人の意思が無視される
- 開示する相手を自分で選べない
- 本人が予期せぬタイミングで起こる
- どこまで情報が広がるか分からない
- 心理的外傷や社会生活への重大な影響をもたらす可能性が高い
上記の例からもわかるように、アウティングは信頼関係を裏切る行為といえます。
カミングアウトを受けた際の情報は、その人だけに打ち明けられた秘密として扱う必要があります。
カミングアウトは強要されるものではなく、個人の自由な選択として尊重されることが大切です。それゆえ、アウティングは相手を傷つける行為になることを知っておきましょう。
アウティングに関する法律
アウティングに関する法律は、「通称パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)」に記載があります。
パワハラ防止法の正式名称は「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」であり、2019年の雇用対策法改正の際、明文化され、大手企業に関しては2020年6月1日から、中小企業に関しては2022年の4月1日から施行されました。
アウティングとなるケース
ここで、アウティングとなるケースを具体的に紹介します。
悪気がないと思っている
アウティングとなるケースで、実はアウティングした側が「悪気がないと思っている」場合があります。
たとえば、カミングアウトを受けた人が「本人は伝えにくいと思い、自分が代わりに伝えてあげよう」などと考えるケースです。
しかし、悪気がなくても、本人の承諾なく他者のセクシュアリティを第三者に伝えることは、アウティングに該当します。情報共有する際には、かならず本人の意向を確認することが重要です。
思い込み
カミングアウトを受けた人が「カミングアウトした本人と親しい人は、当然このことを知っているであろう」と思い、他言するケースも少なくありません。
カミングアウトは個人的な選択であり、その内容や範囲を誰に話すかは本人だけが決められるものです。たとえ親しい間柄であっても、カミングアウトの内容が共有されているとは限りません。
このような認識のズレによるアウティングが、本人に大きな心理的負担を与える可能性があります。
アウティングを防ぐためには、「本人が話したいと思った相手にしか話さない」という原則を徹底することが大切です。また、「念のため確認する」という慎重さを持つことで、思い込みによるトラブルを防ぐことができます。
認識の低さ
アウティングが発生する原因として、自分がアウティングをしているという認識の低さが挙げられます。
おもに以下のような考え方や行動がアウティングにつながる傾向にあります。
- 一人ぐらいに話しても問題ないだろう
- 自分の家族や親しい友人ならいいだろう
- 軽い冗談のつもりだった
- 社内申し送り時に情報共有は必要だと思って
こういった認識や考えをしてしまった際に、社員や関係者がアウティングのリスクを正しく理解し、「他者の個人情報を扱う責任」を感じられることが重要です。
そのためには、定期的な勉強会や啓発活動を通じて、アウティングに対する正しい意識を社内で共有しあう取り組みが求められます。
情報共有のタイミング
社内の申し送り時に、決められているオペレーションに則って情報共有を行った結果、意図せずにアウティングになっていたという場合もあります。
社内の仕組みや取り決めに合わせた行動ではありますが、悪気がない場合と同様に、本人の承諾なく他者のセクシュアリティを第三者に伝えることは、アウティングに該当します。
情報共有する際には、かならず本人の意向を確認することが重要です。
自分も誰かに相談したかった
LGBTQ+当事者から告白されたり、ハラスメントやストーカー被害を受けているなど、自身が当事者ではなくとも誰かに相談したかった場合も考えられます。
悪気がなかった場合や思い込みの場合とは違い、相手からの行為や自分の状況が苦しかった上で第三者に話してしまうケースです。
本人の承諾なく第三者に相談することはアウティングになりますが、自身の状況によっては誰かに相談しないといけない場合もあります。その際は、社内や行政、各団体が行っている相談窓口を活用し、まずは相手が特定されない内容で相談をしてみましょう。
本人がこれ以上一人では抱えきれなかったり、身の危険が迫るような状況の時は、単にアウティングの観点だけでは片づけられないため、状況に応じて相談窓口を活用しましょう。
アウティングに関する罰則
アウティングに関する認識が低い場合はもちろんですが、例え悪気がなかったり、良かれと思ったとしても、アウティングはプライバシーの侵害として民事上の不法行為にあたる場合があります。
また、LGBTQ+当事者にとって、アウティングとともに本人の社会的な評価を下げるような差別的な言動を行ってしまうと、名誉棄損や脅迫罪などの行為にあたる場合もあります。
繰り返しになりますが、他者のセクシュアリティについて「これくらいならいいだろう」や「情報共有だから仕方ない」と自己判断せずに、本人の同意なく第三者に話さないようにすることが大切です。
アウティングが起きた場合の対応
では、社内でアウティングが起きた際に、企業はどのような対応を取ればいいのかのでしょうか。
ヒアリング
まずは、アウティングの被害者本人から詳細な状況を聞き取ります。この際、被害者の精神的な負担を軽減するため、無理に聞き出すことは避け、リラックスできる環境を整えることが大切です。
また、「被害者に原因がある」などの発言は避けましょう。被害者の立場を尊重する姿勢を貫きます。ヒアリングでは以下のポイントを確認します。
- アウティングが起きた日時と場所
- アウティングを行った人とその内容
- 被害者が受けた影響や感情的な反応
その後、加害者、第三者へのヒアリングをします。
いつ、どのような方法で、誰から誰に対してアウティングが行われたのかなど詳細を確認します。
しかしながら、大前提として、ヒアリングをするかしないかは、アウティングをうけた被害者本人の希望にそって行われます。必ず本人の意向を確認しましょう。
社内ガイドラインや制度の見直し
アウティングを防ぐためには、
- 社内ガイドラインの整備と周知
- アウティングの相談もできる相談窓口の設置
- アウティング発生時の対策マニュアルの整備
- アウティングに関する勉強会の実施
社内ガイドラインを整備し、アウティングの定義やリスク、違反時の対応を明記します。
整備後は必要部署や社内全体への周知が必要です。
他にも、相談窓口を設置し、プライバシーを守りながら安心して相談できる環境を整備し、対策マニュアルを作成し、被害者の保護や再発防止策を明確化します。
さらに、ガイドラインに基づく勉強会を実施し、意識啓発を行っていくことも大切です。
また、これら社内ガイドラインやマニュアルなどは、よりよい内容にするため、第三者の意見を交えながら定期的に見直しましょう。
まとめ
アウティングは、LGBTQ+当事者が日常生活を送るなかで常に抱える大きな不安のひとつです。
それは、学校や職場、プライベートな場面など、あらゆる状況で起こりうる深刻な人権侵害行為です。LGBTQ+の非当事者もLGBTQ+の当事者も、アウティングについて正しく理解し、無意識のうちに誰かを傷つけてしまうことのないよう、知識を深めていく必要があります。
株式会社はアカルクは、ダイバーシティ推進のための取り組みをはじめ、LGBTQ+の方がどのような事に配慮が必要なのか、多様性を意識した採用コーチングから、入社後のガイドラインの策定、制度構築、運用を一気通貫で行う人事コンサルティング、キャリア支援といったプロデュース事業を展開しています。
「LGBTQ+について取り組みたいけれど、どんなことから始めたらいいのか分からない」といったご相談や、ピンポイントで「研修」や「外部相談窓口の設置」といったご依頼でも幅広くお受けしています。施策実施・制度策定までの、社内合意形成のプレゼンのお手伝いなども手掛けています。
今回の記事で取り上げたアウティングについて、社内でダイバーシティ推進をするにあたって、様々な課題に関する漠然とした不安や具体的な対策についてもご提案が可能です。
まずは相談でも構いませんのでいつでもお声掛けください。