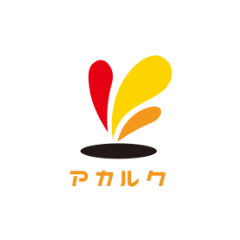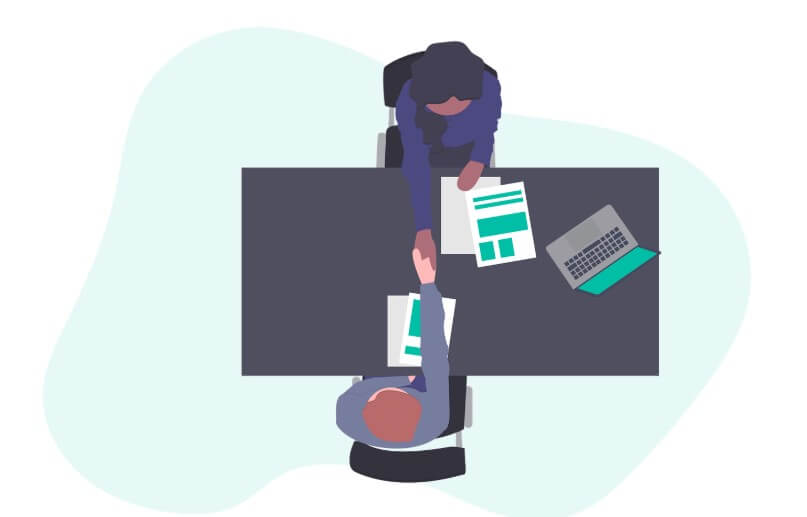性的指向や性自認に関する嫌がらせ行為を意味する「SOGIハラスメント(SOGIハラ)」。このSOGIハラをめぐっては、法律の対応も進化しています。
2020年6月、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、ハラスメント防止措置が大企業の義務に。2022年4月には大企業だけでなく、中小企業を含めたすべての企業に義務化されました。
そして2025年6月、同法律の法改正で厚生労働省は「SOGIハラ」への対応を明確に位置付けました。
特に注目したいのは、2025年6月に施行された法改正でSOGIハラへの対応が明文化されたこと。これは、企業が取り組むべき課題として一気に“可視化”された大きな転換点です。
しかし実際問題、法改正がなされたところで「何から始めれば良いのかわからない」「そもそも何がSOGIハラにあたるのかわからない」という企業は少なくありません。
一体この法制化で何が変わり、企業にはどのような対応が求められているのでしょうか。
本記事では、SOGIハラスメントとは何か、そしてどのような事例が当てはまるのかに加えて、今回の法改正のポイントを解説。また、法改正を受けて企業がとるべき対策も紹介します。
SOGIハラスメント(SOGIハラ)とは
SOGIとは、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字をとった言葉。
「SOGIハラスメント(SOGIハラ)」は、性的指向や性自認に絡めた嫌がらせをを指し、読み方は「ソジハラ」あるいは「ソギハラ」です。
- 性的指向:恋愛・性愛の対象がどんな性別に向くか
- 性自認:自分をどんな性別だと認識しているか
後ほど事例を紹介しますが、SOGIハラの例には性的指向・性自認に関する「差別的な呼称や侮辱・嘲笑」「許可のない暴露(アウティング)」「不当な異動や解雇・昇進外し」などが挙げられます。
SOGIとLGBTQ+の違い
| SOGI | LGBTQ+ | |
|---|---|---|
| 意味 | 性的指向と性自認 | レズビアンやゲイなど |
| 対象範囲 | すべての人 | 性的マイノリティの人々 |
| 当事者意識 | 誰もが「自分のSOGI」を持っている (他人事ではない) |
主にLGBTQ+当事者が中心 |
SOGIと似た言葉に、以下の頭文字をとったLGBTQ+があります。
-
-
- レズビアン(Lesbian=女性が恋愛対象の女性)
- ゲイ(Gay=男性が恋愛対象の男性)
- バイセクシュアル(Bisexual=両性が恋愛対象の人)
- トランスジェンダー(Transgender=生物学的な性と性自認が異なる人)
- クエスチョニング(Questioning=性的指向・性自認が定まっていない人)
- クィア(Queer=上記に当てはまらない人)
- +(上記では表現できない多様な性のあり方を持つ人)
-
主に性的マイノリティに焦点を当てたLGBTQ+と異なり、SOGI(性的指向と性自認)はすべての人に関わる性のあり方を指します。
昨今は「誰もが当事者になり得るハラスメント」として捉えてもらうために、「LGBTQ+ハラスメント」ではなく、あえて「SOGIハラスメント」という言葉が使われるケースも増えてきています。
SOGIハラスメントにあたる2つの事例
「SOGIハラスメント」という言葉を聞いても、実際にどのような事柄が該当するのか、イメージしにくい人も多いかもしれません。
ここでは、SOGIハラスメントとして認定された事例を2つ紹介します。
トランス女性労働者を不当解雇し裁判となった事例
本件は2002年、「トランス女性(※)」に該当するAさんが、性自認に沿った勤務を希望した際、企業側から拒否された事例です。
Aさんが「女性的な服装で勤務したい」と伝えると、会社側はそれを拒否。Aさんはそれに従わず、女性的な服装や化粧で出社したところ、業務命令違反を理由に懲戒解雇を命じられました。
裁判所は、性自認に基づいた働き方を求めたAさんの要望には合理性があり、懲戒解雇に相当するほどの企業秩序違反は認められないと判断しました。
※当時は「性同一性障害」という医学的診断名が使用。現在は「性別不合」の言葉を用いる。
性的指向に関する差別的発言がハラスメント認定された事例
本件は2025年、性的指向に基づく否定・侮蔑的な言動がハラスメント行為にあたると判断された事例です。
学童支援員が昨年2024年、「自分はバイセクシュアルだ」ということを明かしたうえで、同じLGBTQ+当事者の子どもへの相談に対応。その結果2024年7~11月、教育委員会職員から以下のような発言をされました。
「子どもたちの前でLGBTの話をするな」
「子どもたちにLGBTはいない」
これらの発言は、性的指向に基づく否定・侮蔑的な言動として教育長が謝罪。顧問弁護士による調査でも「ハラスメント的行為」と結論づけられました。
参考:朝日新聞「LGBTQの学童支援員に「自分をさらけ出すな」不適切対応と認定」
「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」の概要とSOGIハラスメントの扱い
SOGIハラスメントに関連する法律はいくつかありますが、その中でも今回取り上げるのが「労働施策総合推進法(パワハラ防止法)」です。
同法律は2020年6月に大企業・自治体に適用された後、2022年4月には中小企業にも適用範囲が拡大。
策定された当時、以下の内容がハラスメントに該当することが明示されました。
- 人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことを含む。
- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること。
2020年時点では、性的指向や性自認に関する配慮は示されていたものの、「SOGI」という概念が正面から取り上げられることはありませんでした。
パワハラ防止法改正によるSOGIハラスメント対応の3つのポイント
2025年6月、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の改正において、厚生労働省は以下の内容を明記しました。
-
-
- カミングアウトを禁止・強要・強制する行為はパワーハラスメントに該当
- 顧客から労働者へのSOGIに関連するハラスメントがカスタマーハラスメントに該当
- 就職活動中の学生へのSOGIに関連するハラスメントの防止が必要
-
今回、SOGIについて正面から明記されることになった背景には、LGBT法連合会など当事者団体による働きかけもあるでしょう。また、SOGIハラを巡る社会的認識の高まりも大きく影響しています。
上記3項目は、どのような内容を指しているのか。以下で詳しく解説します。
カミングアウトの禁止・強制もパワハラに
職場で性的指向や性自認を他人に「言うな」と禁止すること、「言え」と強制・強要することがパワハラに該当することが明記されました。
LGBTQ+などの当事者は、自身のSOGIを他人にカミングアウトするかどうかを慎重に考えていることが多いです。それにも関わらず、「なぜ言わないのか」や「隠すのは良くない」などの無理解な発言は、精神的負担となります。
また、昨今はカミングアウトを禁止することも問題視されてきています。
今回の決議により、当事者の自己決定権を守る立場が明確化されたと言えるでしょう。
顧客から労働者へのSOGIハラは「カスタマーハラスメント」に該当
顧客や取引先などによるSOGIハラスメント(差別的発言や暴言、嘲笑など)がカスタマーハラスメント(カスハラ)に該当することが明記されました。
従来、顧客や取引先によるSOGIハラは見過ごされがちでしたが、労働者の尊厳を傷つける行為であることが法的に認識されました。
企業側は「お客さんの言っていることだから」と放置せず、対応する必要があります。
就活生へのSOGIハラの防止も必要
面接時の服装やメイク、話し方などを根拠に、性別の固定観念で就活生を評価・排除するケースは珍しくありません。
しかし今回の法改正で、採用活動の場において、就活生に性的指向や性自認を質問すること、また差別的な対応をすることはSOGIハラスメントにあたることが明記されました。
採用に関わるすべての担当者がこれを意識し、面接だけでなく、インターンシップや説明会などの選考プロセスにおいて「無意識のSOGIハラ」を起こさないことが求められます。
企業ができるSOGIハラスメント対策例
兵庫県は、「LGBTQ+(性的マイノリティ)が働きやすい職場づくりの取組み状況」についてのアンケート調査を実施。
その結果、県内企業の4割がSOGIハラ防止について何も対策していないことが明らかになりました(従業員50人以上の5320社のうち930社が回答)。
出典:読売新聞オンライン「性的少数者への「SOGIハラ」対策、義務化されても兵庫の企業4割が何も講じず」
SOGIハラへの対応は、放置すれば企業イメージの毀損や訴訟リスクも高いことから、昨今は「対策するのが当たり前」という認識が強まっています。
企業がとれるSOGIハラ防止対策として、以下が挙げられます。
- 社内制度・ハラスメント研修の実施
- 相談体制の整備
- カスタマーハラスメント対策にSOGIを明記
- 顧客への周知
- 採用・面接ガイドラインの見直し
- 応募者へのメッセージ
たとえば「カミングアウトを迫る・拒否すること自体がハラスメントになること」自体を知らない従業員は少なくありません。
SOGIに関するハラスメント研修の場を設けることで、「何がハラスメントになるのか」という認識の共有が可能となります。
また、社内のカスハラ対策方針に 「SOGIに関する不適切な発言や行動も対象」と明記し、トラブル発生時の手順(同席者の交代・退席指示など)を策定することも効果的です。
そのほか、就活生へのSOGIハラ防止に関しては、面接官に「避けるべき質問」の指導をしたり、ダイバーシティ推進方針を採用ページや募集要項に明記したりするのも1つの方法です。
なお、以下は東京都のハラスメント防止対策として、「SOGIハラになりうる言動」についてまとめた動画です(弊社アカルク監修)。
具体的なSOGIハラ防止対策についても触れているので、ぜひご覧ください。
SOGIハラスメントへの対応を通して、誰もが働きやすい職場に
2025年の法改正をきっかけに、「SOGIハラスメント」は、企業が明確に対応すべき社会課題となりました。
職場での何気ない言動が、人の尊厳を傷つけることもあります。「知らなかった」「悪気はなかった」では、もう済まされない時代です。
企業のダイバーシティ推進において、SOGIへの配慮は欠かせないテーマです。誰もが自分らしく、安心して働ける環境は、従業員のエンゲージメントや生産性の向上にもつながります。
アカルクでは、SOGIに関する制度整備や研修設計のご相談、職場づくりのサポートも行っています。
「LGBTQ+関連の制度策定に悩んでいる」「SOGIハラ対策の重要性は理解しているが、何から始めれば良いのかわからない」という企業様は、お気軽にご連絡ください。
執筆者:佐藤ひより
大手メーカーの海外営業職を経験後、2018年にライターとして独立。フリーランスとして多様な価値観や働き方に触れる中で、「一人ひとりが自分らしく生きられる社会」に関心を持つように。現在は、キャリア・ビジネス・ライフスタイル分野を中心とした記事制作に携わっています。