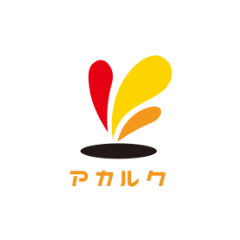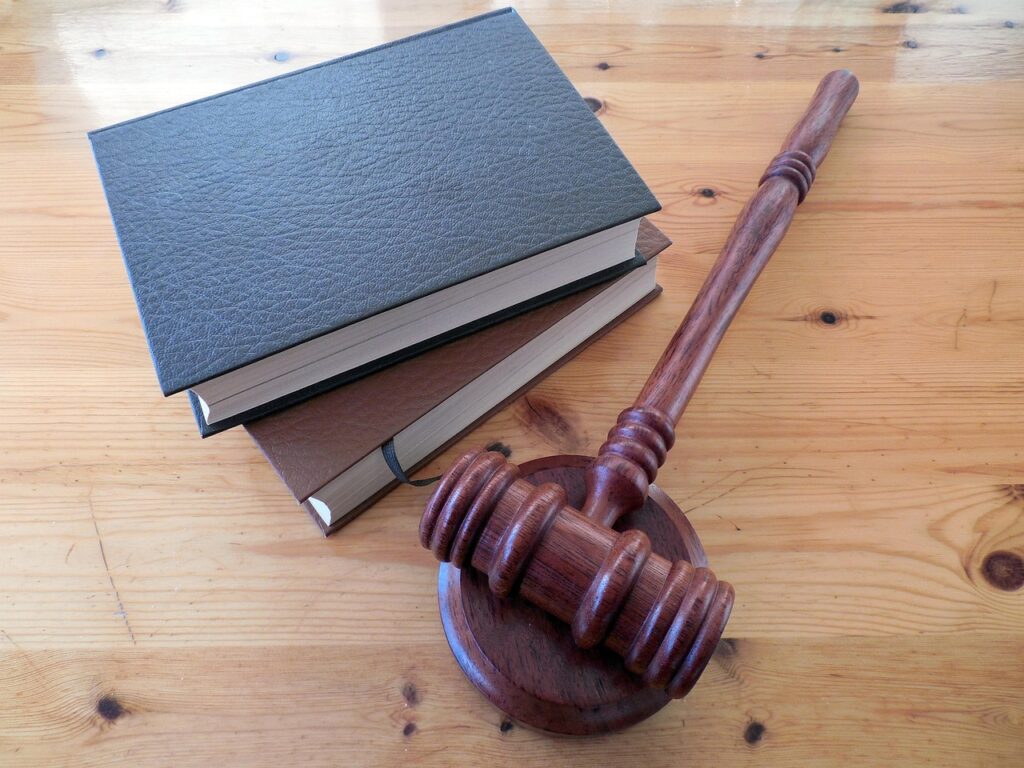「誰と人生をともに歩むか」
それは多くの人にとって、ごく自然で個人的な選択です。
しかし、同性カップルにはその選択が法的に認められていません。税制・医療・相続・子育てなど、さまざまな場面で不利益を受ける現実があります。
この状況を変えたいと、全国5地裁で起こされたのが「結婚の自由をすべての人に訴訟」です。
地裁では判断が分かれましたが、高裁では「違憲」または「違憲状態」とする判断が相次ぎ、現在は最高裁での審理が進んでいます。
同性婚の法制化をめぐるこの動きは、「誰が家族と認められるか」という問いを通じて、社会全体の制度設計や、組織が持つ価値観にも影響を及ぼすものです。
福利厚生、税制、医療・教育など、法的婚姻を前提とした制度は社会のあらゆる場面に根付いています。同性婚が認められることで、その見直しが必要になる場面も増えていくでしょう。
そこで本記事では、同性婚訴訟の背景や現在の状況を整理するとともに、この問題が企業や社会にどんな変化をもたらすのかを考えていきます。
同性婚訴訟では何が争われている?【簡単に整理】
2019年から全国5つの地方裁判所(札幌・大阪・東京・名古屋・福岡)で起こされた「結婚の自由をすべての人に訴訟」。
この訴訟で争点となっているのは、憲法で定められた以下の権利です。
- 憲法14条(法の下の平等):すべての人は平等に扱われるべきである
- 憲法24条1項(結婚の自由):婚姻は両性の合意のみに基いて成立するものである
- 憲法24条2項(個人の尊厳と家族の平等):結婚・家族制度は、個人の尊重と平等をもとに作るべきである
同性婚を認めない現在の制度は、上記の憲法に違反している=違憲であるという主張です。
そのほか、原告側は憲法13条が保障する「個人としての尊重」や「幸福を追求する権利」にも反していると主張しています。
誰と人生をともにするかという選択は、人が自分らしく生きるための根幹にあるもの。この訴訟は、単なる制度上の課題ではなく、個人の尊厳に関わる問題だとして注目を集めています。
なぜ地裁では判断が割れたのか?判断は高裁へ
| 裁判所 | 判決日 | 憲法14条 (平等) |
憲法24条1項 (結婚の自由) |
憲法24条2項 (個人の尊厳と家族の平等) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌地裁 | 2021年3月 | 違憲 | 合憲 | 合憲 |
| 大阪地裁 | 2022年6月 | 合憲 | 合憲 | 合憲 |
| 東京地裁 | 2022年11月(一次) 2024年3月(二次) |
合憲 | 合憲 | 違憲状態 |
| 名古屋地裁 | 2023年5月 | 違憲 | 合憲 | 違憲 |
| 福岡地裁 | 2023年6月 | 合憲 | 合憲 | 違憲状態 |
地裁レベルで判断が割れたことから、同性婚をめぐる制度が未整備なことがわかります。
それぞれの裁判所が異なる憲法解釈をしたのには、さまざまな背景が考えられます。性的マイノリティに対する理解度や、制度の空白地帯への捉え方が裁判官ごとに違うのも1つの理由ではないでしょうか。
地裁によって判断が異なることは、「住む場所によって法的な扱いが変わる」という不公平感を生みかねません。
だからこそ、統一的な判断が求められる最高裁の役割が、今非常に注目されているのです。
なぜ高裁は「違憲」で揃ったのか?社会の変化とその影響
地裁では判断が分かれた同性婚訴訟ですが、高裁では5件すべて「違憲」または「違憲状態」の判断となりました。
なお、地裁と高裁でこれまでに出された11件の判決のうち、 7件が「違憲」、3件が「違憲状態」、1件が「合憲」と判断が分かれています。
高裁の判決文では、こうした判断の背景について詳細には言及されていません。しかし、近年の社会的変化や国際的な動きを踏まえると、以下の要素が影響したという見方もあります。
- 社会全体で性的マイノリティへの理解が進んでいること
- 同性カップルに対する法的保障の欠如への問題意識が広がっていること
- 国際人権基準と日本の現状との乖離に対する危機感
- 地裁で結論が割れたことによって、上級審における統一的な判断が必要とされたこと
- 同性カップルが直面する具体的な不利益の実態が明らかになったこと
特に近年では、憲法14条(法の下の平等)に基づき、同性婚を認めない現行制度が「合理的理由のない差別」と評価する傾向が強まっています。
また、婚姻届が受理されないことにより、同性カップルは以下のような不利益を受けています。この実態が明らかになったことも、違憲判断の後押しになったと考えられるでしょう。
- 配偶者控除や相続税の優遇が受けられない
- 健康保険の扶養に入れない
- 配偶者として医療の同意や面会ができない
- 遺族年金が受け取れない など
こうした社会的背景の変化、そして同性カップルの不利益に関する認知度の高まりが、高裁における違憲判断の広がりに一定の影響を与えた可能性はゼロではありません。
高裁で「違憲」の判決が出たにも関わらず、最高裁へ上告する理由
5件の訴訟について、高裁はいずれも「違憲」または「違憲状態」とする判断を示しました。
これを受けて、控訴人たちはすべての事件について最高裁に上告しています(2025年8月時点、最高裁判決はまだ出ていません)。
高裁で制度の違憲性が指摘されたにもかかわらず、なぜ最高裁への上告が行われたのでしょうか。
その背景には、控訴人たちが単に賠償を求めているのではないのが大きな理由です。同性婚の法制化を実現するために、最終的な憲法判断を求めているという意図があります。
同性婚の法制化実現の鍵となる最高裁の判決
仮に最高裁が明確に「違憲」と判断すれば、同性婚を認めていない民法や戸籍法の改正を求める声は一層強まると考えます。
理由は、違憲状態を放置することが「立法不作為(※)」と見なされる恐れがあるためです。
また、日本経済新聞社の世論調査(2023年実施)では、同性婚に賛成する人の割合は65%と過半数。さらに「G8の中で同性婚が法制化されていないのは日本とロシアのみ」という国際的な視線も厳しさを増しています。
企業や自治体レベルでもパートナーシップ制度が広がっており、上述の背景からも、政治が動く可能性は十分に考えられます。
実際、自民党は慎重な姿勢を続けているものの、同性婚に前向きな野党も存在しているのが現状です。政治的な構図にも、変化の兆しが見えています。
※国会が憲法で定められた立法義務を怠り、必要とされる法律を制定しないこと
出典:日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68780580W3A220C2PE8000/)
ただし「グレーな表現」で立法が動かない可能性も
ただし、最高裁が必ずしも明確な「違憲」判断を下すとは限りません。「違憲状態」や「将来的に違憲となる可能性がある」といった慎重な表現にとどまる可能性もあります。その場合、法改正に向けた動きが鈍ることが想定されます。
また、憲法判断は通常、結論が出るまでに長い時間を要します。そのため、実際に何らかの政治的・法的動きがあるのは、早くても2026年以降になると予測できるでしょうか。
法制化で求められる企業の変化とは?今から備える制度対応
同性婚が法制化された場合、企業・制度側にはさまざまな変化が求められます。以下は、法制化で想定される社会の対応や変化について紹介します。
1. 企業の福利厚生・社内制度の見直し
- 家族手当・扶養手当の対象拡大
- 結婚休暇・慶弔休暇制度の適用範囲の拡張
- 健康保険や厚生年金の運用見直し
- 就業規則・人事システム
家族手当・扶養手当を「戸籍上の配偶者」に限定している企業は少なくありません。もし法制化された場合、同性配偶者もその対象となる可能性があります。結婚休暇や忌引き、配偶者の出産休暇なども同様です。
また、厚生年金の第3号被保険者(専業主婦/主夫的な立場の人)や健康保険の扶養認定も、同姓配偶者を想定した運用の見直しが必要になります。
2. 公的制度・行政サービスでの対応
- 戸籍制度の修正
- 各種申請書・届出様式の変更
- 税制・年金制度の適用対象の見直し
現在の戸籍は「夫・妻」の表記を前提としています。法制化により、同性夫婦にも対応可能な形に修正される可能性があります(たとえば「配偶者」表記に統一するなどの性別中立な言い換え)。これは、行政手続きで必要な各種書類も同様です。
また、所得税の配偶者控除や遺族年金に関する制度が、同性配偶者に適用される可能性も出てきます。
これらの制度対応は、単なる書類上の変更ではなく、「誰が家族か」を法的に認め直すという社会全体の価値観の転換と言えるのではないでしょうか。
3. 医療・介護・子育て・相続への影響
- 医療現場での対応
- 子育て・養子縁組への対応
- 相続制度への反映
これまで同性配偶者は法的な家族として扱われないため、手術の同意や入院の面会が制限されるケースもありました。法制化により家族として認められれば、こうした制約が見直される可能性があります。
そのほか、同性カップルが共同で養子を迎えることが可能になれば、学校での保護者記入欄の表記の見直しも必要となると考えられます。
また民法上、同性配偶者が法定相続人として認められるようになれば、遺言がなくても相続できるようになるかもしれません。
企業に求められる姿勢とは?
同性婚の法制化が現実的な可能性として存在している以上、企業は当事者意識を持つ必要があります。
制度の転換点に差しかかっている今、企業に求められる姿勢として以下が挙げられます。
- 法改正を待たずに、先回りして「多様な家族」に対応する姿勢
- 社内制度やルールを見直すアップデート意識
- 「人権尊重」の観点を持った対応
- 声を上げにくい人がいることを前提にした配慮
制度の改正を待つのではなく、先んじて多様な家族の形に向き合う姿勢が求められています。
特に婚姻制度に関わる福利厚生や社内ルールは、「異性婚を前提とした作り」になっているケースも少なくありません。今後の見直しは避けられないでしょうか。
さらに、社員が安心して自分らしく働ける職場づくりのためには、「制度」だけでなく「文化」の変化も必要です。
声を上げにくい立場の人を前提とした配慮ができるかどうかが、重要な時代となってきています。
企業が社会の一部としてできること
今後、最高裁の判決によって婚姻制度が大きく変わる可能性があります。しかし、その変化を「待つ」だけではなく、企業として先回りして備えることも大切です。
誰もが尊重され、自分らしく働ける職場をつくるために、企業もまた当事者としてこの社会課題に関わっていくことが求められています。
アカルクでは、LGBTQ+の社員がいることを前提とした制度設計や社内研修のサポートを通じて、表面的な対応ではなく「実のある取り組み」をご支援しています。
「自社に合った制度を整えたい」「まずは話を聞いてみたい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
執筆者:佐藤ひより
大手メーカーの海外営業職を経験後、2018年にライターとして独立。フリーランスとして多様な価値観や働き方に触れる中で、「一人ひとりが自分らしく生きられる社会」に関心を持つように。現在は、キャリア・ビジネス・ライフスタイル分野を中心とした記事制作に携わっています。