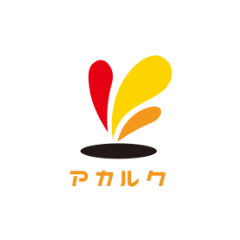近年、多くの企業がダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DEI)推進に本腰を入れ始める中、LGBTQ+に関しても「当事者のリアルな語り」が求められる機会が増えてきています。LGBTQ+当事者が「LGBTQ+推進の担当者」として、社内研修や制度整備の前線で活躍する姿も見られるようになってきました。
私自身もLGBTQ+当事者であり、企業のDEI推進に関わっている一人です。
日々の実践のなかで、当事者だからこそ担える役割の手応えを感じる一方で、「当事者であること」に付随するプレッシャーや葛藤が生じる場面にも、たびたび直面してきました。
こうした経験を通じて見えてきたのは、「語り手」としての期待が寄せられることで、当事者が心理的・社会的リスクにさらされてしまう可能性があるという現実です。任命された立場で語ることもあれば、熱意から自ら語ろうとすることもあるかもしれませんが、いずれの場合も、その背後にはあまり語られてこなかった“ジレンマ”が潜んでいることもあります。本記事は、企業でDEIやLGBTQ+に関する取り組みを推進する立場にある方、特に人事部門やDEI推進担当、LGBTQ+理解促進を担っている皆さまに向け、当事者が理解促進を担う際に直面しやすい葛藤やリスクについて紹介しながら、企業としてどのように支えられるか、そして外部支援の活用という選択肢についても考えていきたいと思います。
「当事者性=推進力」とされやすい現実
社内での理解醸成が不十分な状態で、LGBTQ+の当事者がカミングアウトを伴って社内におけるLGBTQ+の推進担当に就くと、その人が偏見や揶揄の矢面に立たされてしまう可能性があります。LGBTQ+に関する固定観念に基づく誤解や排除の言葉が、その担当者個人に向けられてしまうこともあるかもしれません。
「当事者なら気持ちがわかるだろう」「リアルな言葉が伝わりやすいはず」──。
こうした期待とともに、LGBTQ+当事者が「当事者担当者」として任命されるケースは珍しくないようです。本人自身も「役に立ちたい」「同じような思いをしている人の力になりたい」との思いから快く引き受けることが多いのではないでしょうか。
しかしその一方で、「当事者であること」自体が役割と化してしまう構造には注意が必要です。
これはLGBTQ+に限らず、「子育て中だから育児支援担当に」「外国籍だから多文化共生担当に」といった、他のダイバーシティ領域にも見られる傾向かもしれません。属性に基づく任命は、当事者の視点という強みを活かす一方で、本来業務として分担すべき負担やリスクを“その人のパーソナリティ自体”に押しつけることにもなりかねません。
目的があいまいなまま、「頼れるから」「詳しいから」といった理由で活動を任され続けると、当事者はやがて燃え尽きてしまうこともあります。制度的な裏付けがないまま、熱意や善意だけで進めることには注意が必要です。
ある企業では、「当事者だから」と任命された社員が、研修企画・講師・社内相談窓口までを一手に担っていたそうです。
最初は「力になりたい」という気持ちから始めたものの、徐々に疲弊し、異動を機にその役割を手放すことになったといいます。
後任も見つからず、せっかく芽吹いた取り組みが頓挫してしまったという事例もあるようです。このようなケースは、決して少なくないのかもしれません。
加えて、DEI推進の枠組みとは別に、ERG活動やアライ活動の中でも、LGBTQ+当事者が“語る役割”を求められる場面も見受けられます。当初は「自分の意思で語っている」つもりでも、繰り返されるうちに語ることが“当たり前”となり、知らず知らずのうちにプレッシャーや疲弊につながってしまうこともあるかもしれません。
とくに、ERGやアライ主導のイベントであっても、当事者にばかり語りが集中すると、「語らない選択」が難しくなり、“無言の義務”としてのカミングアウト状態に陥ってしまうことも考えられます。
こうした状況にも企業は目を向け、「任意の場面でも語らない自由を保障すること」や「非当事者の積極的な役割分担」といった配慮が求められているのではないでしょうか。
圧倒的な“当事者の語り”とそのパワー
一方で、当事者の語りにはやはり他にはない力もあります。とくに、社内の風土や歴史、人間関係を理解している社内の当事者の言葉は、リアリティと説得力を持って受け止められることが多いのではないでしょうか。「この人が言うなら耳を傾けてみよう」と信頼が高まることもあり、当事者だからこその共感力や発信力が発揮される場面も少なくないようです。
たとえばある企業では、当事者の社員が自らの経験をもとに、職場向けのハンドブックを作成したといいます。当事者だからこそ気づけた注意点や工夫が盛り込まれた内容が、非常に有用であったとのことです。このように、当事者が中心となって進めた取り組みは、時に大きな化学反応を生む可能性もあるかもしれません。
そして、何より忘れてはならないのは、当事者の中には「自分の仲間、自分より下の世代のLGBTQ+に、同じ思いをしてほしくない」「もっと生きやすい社会を渡していきたい」
「セクシュアリティごと自分を受け入れてくれた会社に恩返しがしたい」といった、強い思いを原動力に活動している人たちがいるということです。私自身もその一人です。かつての自分のように孤独や息苦しさを感じながら働く人が一人でも減ってほしい──そんな願いが、今の活動の大きな動機になっています。これは、義務感や“当てがわれた役割”としてではなく、やりがいや希望につながっている感覚でもあります。
だからこそ企業は、当事者の語りの“効果”だけに注目するのではなく、その語りが本人にどのような負荷を与えているのかにも同時に目を向けてほしいのです。やりがいや意欲があるからこそ、無理をしてしまうこともあるかもしれません。負荷に気づかれないまま、孤立感や燃え尽きへとつながってしまうこともあるでしょう。
当事者に「任せっぱなし」にするのではなく、継続的な対話やケア、周囲の支えによって、語ることが本人にとっても“持続可能”なものであり続ける──そんな姿勢が、企業に今求められているのではないでしょうか。
カミングアウトの判断は慎重に:メリットとデメリット
LGBTQ+当事者が「DEI担当」や「LGBTQ+の推進担当」を任された場合、避けて通れないのが「カミングアウトするか、しないか」という選択です。どちらにも利点と課題があるため、慎重に判断されている方も多いのではないでしょうか。
社内でのカミングアウトのメリット
- 自身の経験に基づいた言葉で語れる
- 隠さなくてよいことで心理的負担が軽減される
- 他のLGBTQ+当事者にとって希望や安心感となる可能性がある
社内でのカミングアウトのデメリット
- プライベートな質問や詮索にさらされる可能性がある
- 昇進や配置に影響するなど、キャリア面での不安がある
- 「当事者として語ること」が無意識の義務になる場合がある
仕事熱心な当事者ほど、「自分の言葉で伝えたい」という気持ちから、内省が深まる前にカミングアウトしてしまうこともあるかもしれません。しかし一度語ると、その情報のコントロールは難しくなるため注意が必要です。
そのため、「なぜ語るのか(目的)」「誰に語るのか(範囲)」を明確にし、情報共有のルールや相談先を整えておくことが重要になるのではないでしょうか。また研修等でカミングアウトが行われる際には、その情報を誰まで共有してよいかといった点を事前に確認・合意しておくことも望まれます。
善意の「抑制」もまた、ハラスメントに(法改正案の動向と注意点)
語るリスクと同様に、「語らない」選択を妨げることも、大きな問題につながる可能性があります。たとえば、上司や人事が「今の社内では理解が進んでいないから、語らないほうがいいのでは」とアドバイスをすることがあるようですが、それが善意であっても、本人の意思を妨げるような言動は慎重に扱う必要があるといえるでしょう。
2025年6月3日に参議院厚生労働委員会で附帯決議が可決され、6月4日に成立、6月11日に公布された労働施策総合推進法の改正案では、以下のような内容がハラスメントに該当する可能性があるとされています。
- カミングアウトの強制
- カミングアウトの抑制
- 就職活動中の学生に対するSOGIハラスメント
これらは今後、国のハラスメント防止指針において「性的指向・性自認等に関するハラスメント」の類型として明記される方向で整理が進められています。
つまり、「語ること」「語らないこと」のいずれの選択も、本人の意思が尊重されない場合にはハラスメントと見なされる可能性があります。
今回の法改正は、当事者が自らの意思で安心して選択できる環境づくりを後押しする1つと言えるのではないでしょうか。
非当事者が推進担当を担うことの意義と方法
DEI推進やLGBTQ+に関する取り組みを当事者だけに任せるのではなく、非当事者も共に関わっていくことは、活動を持続的に進めていくうえで大きな力になります。非当事者の方に推進していただくことで、当事者の心理的・社会的な負担を軽減できるだけでなく、組織全体の理解促進やアライの巻き込みにもつながるからです。
社会全体の約90%は非当事者であり、多くの人が関わることで組織や社会を変えていけるという現実があります。一方で、当事者だけが声を上げ続ける状況では、取り組みが一部の人に偏り、継続が難しくなることもあります。
こうした中で、非当事者が関わる際には、当事者の声を思い込みや偏見で代弁や上書きしたりしないようにしたり、お互いの立場や経験を尊重し合いながら進めることが最も重要ではないでしょうか。当事者の声を一緒に支え、必要に応じて役割を分かち合うことで、互いに無理のない形で取り組みを続けやすくなります。「誰かのために」ではなく、「一緒につくる」姿勢が、多様性を尊重する組織づくりにつながっていくのではないでしょうか。
まとめ
ここまで、LGBTQ+当事者が担当者として推進活動に関わることの持つ力と、その一方で直面しやすい課題やリスクについて見てきました。
当事者が語ることも語らないことも、どちらも尊重される職場こそが、真にインクルーシブな職場といえるのではないでしょうか。
LGBTQ+当事者で推進の担当者として長く活躍し続けるためには、守られた環境の上で安心して力を発揮できることが何より重要だと考えられます。
だからこそ企業には、そういった環境を整える責任があるのではないでしょうか。その一つの方法として、外部パートナーと連携し、担当者が“削られずに続けられる”仕組みを構築することが、長期的なDEI推進につながるかもしれません。
株式会社アカルクは、そうした企業や組織の取り組みを支援するパートナーとして、ガイドライン策定や研修設計、制度整備のサポートを行っています。また、外部窓口も運営し、当事者担当者自身からの相談も受け付けています。
持続可能なDEIの土台を共に築きたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
執筆者:ししまる
IT中堅企業の人事としてDEI施策全般を主導する傍ら、社内外でLGBTQ +の支援活動にも従事。企業内担当者として、さらにイチ当事者としての目線からも、自分らしく働ける組織づくりについて発信します